「京都大学ラグビー部六十年史」(昭和62年・1982年発行)寄稿文
————————————————————-
かつて、学生時代にラグビーを思い切りやった事が、その後の人生を生き抜く体力や精神力を与えてくれた、という言葉をよく耳にします。確かにその通りだと思います。
しかし、私に言わせれば、ラグビーの恩恵は、体力とか精神力とか言った単純な言葉だけで表現するには余りにも豊かすぎる、と思うのです。この体力とか精神力とか言った言葉が、ラガーメンに、何か強いけれども頑固な人間、というイメージを与えています。しかし現実は逆でしょう。本当にラグビーを理解し、愛した人々は、世の中で最も柔軟な感性を持った人間に成長しているはずです。
それは当然なのです。
ラグビーというスポーツの特徴をひと言でいうなら、「人間が自然に持っている能力の全面解放」という事です。走る、投げる、蹴る、ぶつかる、倒す、奪う、十五人で協力してやる。たったひとりになってもやる。… 未だ社会のルールなど全く知らない子供達にボールを一つ与えて遊ばせてやると必ずラグビーの原形となる動きをします。
ラグビーというスポーツは、先ず、自然に欲することは何をやっても良い、という大前提から出発し、もちろんそれだけだと無秩序と混乱でしかないところから、この大前提を可能な限り生かしながらルールができて行ったスポーツだと思うのです。
だから、この人間としての解放感を、観念やイメージからではなく、自分の肉体を通して体験している事は、大げさに言えば、その人間の、世界観に迄つながって来るのです。
私は大学卒業後、テレビディレクターという、同期の仲間の中ではチョット毛色の変った仕事に入り、今も、映画・テレビ・コマーシャル等の監督をしています。
この仕事は、映像や音楽に依ってイメージを創造してゆく仕事ですから、一見、ラグビーの様な武骨なスポーツとは正反対の世界の事の様に見えるかもしれません。
しかし、そうではないのです。
狭い範囲で言えば、映像を編集してゆく時のリズム感覚などは、バックスがサイドステップを踏んで一瞬トイメンをズラせてゆく時のあの感覚を深く繋がっています。若い頃に、ラグビーを通して私の肉体の中で解放されたリズム感覚は、そのまま、無意識の内に編集感覚の中に生きるのです。
人間の脳細胞は五十億近くが使われないままに眠っている、と言われますが、その眠っている脳細胞を活性化する回路が、若い頃にラグビーの辛い練習や試合を通じて開かれているのです。さらに、我々の仕事で最も重要で責任の重い事は、作品を作る監督の人間観、世界観です。一人の意見、一つの意志を、作品を通じて多くの人々に対して表明してゆく訳ですから、テーマが如何なるものであっても、その根底に流れる人間観は重大です。私の場合、ラグビーの体験を通じて得た人間観は私の全作品に流れていると思います。
「人間性の全的解放とそこから生まれたルール」よく、ラグビーは、一人のレフェリーに絶対服従するスポーツだ、と言います。しかし、この言い方は正しくありません。
ラグビーの様に、人間性の全的解放、という思想を根底に持っているスポーツでは、どんなにルールを厳格にしても、いくらレフェリーの数を増やしても、絶対的に正しい正誤の判定を下す事などできないのです。
だからこそ、試合中は、たった一人の人間の判定に全てを委ねよう、という思想が生まれたのでしょう。レフェリーだって一人の人間、誤りもすれば、感情的にもなる。しかし、試合という限られた時の間は、全てをこの一人の人間に委ねようではないか。… この考えの背景には、選手一人一人が、自分自身の解放のために、自分自身を律するという姿勢がなければなりません。ルールというものも本来、こうして生まれなければならないと私は思います。
自分自身の解放、と相手に対する思いやり、この一見矛盾する事柄を調和させてゆくための思想がラグビーにはあると思うのです。
私は、四十歳を過ぎた今もささやかにラグビーをやっています。私の筋肉や骨はもう苛酷なぶつかり合いや格闘には耐えられませんので、今はほとんどがトイメンなしのシャドウプレイです。でも、練習のある時は本当にワクワクします。気持ちがいいのです。そして時々、京都大学に入ってラグビーを始めたばかりの頃の気分を想い出します。
映像の仕事をしていると普段は頭の中に様々な映像が渦巻いて、それを軸に世界が動いています。ところがラグビーをやると一瞬目が覚めるのです。頭の中のイメージが一度すっかり洗い流されて、その虚空に又新鮮なイメージが一度すっかり洗い流されて、その虚空に又新鮮なイメージがわき起こって来ます。
私は、ラグビーに感謝しています。(昭和三十八年卒)
 |
 |
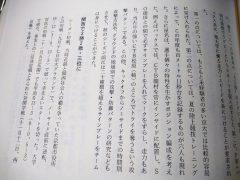 |
|---|---|---|
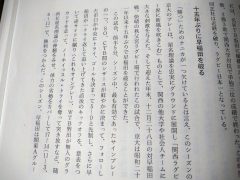 |
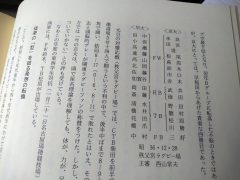 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |








